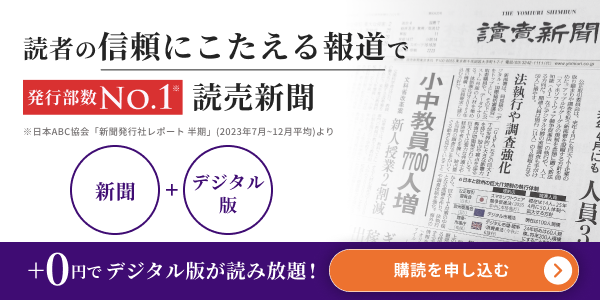[演芸おもしろ帖]巻の五十七 東京にも続々進出中、キリがなくて面白い上方落語をもっと楽しみたい
完了しました
「よみらくご」総合アドバイザー、演芸評論家の長井好弘さんが、演芸愛いっぱいのコラムをお届けします。
長井好弘の演芸おもしろ帖
首都圏で生の上方落語を楽しむ機会がじわりじわりと増えてきた。
上方の中堅若手が東京で会を開く、東西若手の交流会が活発化する、さらには東京に拠点を移す上方落語家も出てきた。
落語好きには関東も関西もない、まだ聴いたことのない古典ネタ、奇想あふれる新作を演じるというなら行ってみたいし、異能有能な若手、知る人ぞ知るベテランの高座にも触れてみたい。今日も遠く京阪神の地で、知らない落語家が知らないネタを演じ、地元の観客が笑い転げているかと思うと、うらやましくて、ねたましくて、居ても立ってもいられない。
だが、時間にも資金にも限りがある。交通費、宿泊費も含まれているのだろう、東京で催される上方落語の会の木戸銭は大御所でも若手でも割高になる。可能であれば、毎年四半期に一週間ぐらい、上方寄席巡りをしたいなあと思わずにはいられない。

「電気踊り」の初代小南、艶っぽい芸の二代目小文治…
だから、東京を拠点に上方落語を演じてくれる
古くは東京落語の団体が分裂、合同を繰り返していた明治末から昭和初期にかけて、「助っ人」として上方落語家が呼ばれるということがしばしばあった。だが、当時の東京の観客は関西弁に慣れておらず、上方落語の軽快なテンポについていけない。「何言ってるか、わからない」という客が大半を占めていた。そういう状況の中で生き残った上方落語家は、無数の豆電球を体に巻きつけた「電気踊り」が売り物だった初代桂
昭和の戦後には、ラジオテレビの普及もあり、関西弁に慣れた東京の観客は、新喜劇や漫才など、いわゆる吉本系のお笑いを中心に関西演芸に親しむようになった。
六代目笑福亭

東京の寄席ファンに親しまれたのは二代目桂小南(1920〜1996年)である。関西出身で、三代目三遊亭金馬の弟子になった小南は、上方落語を東京の観客にわかりやすいように手直しして演じてくれた。1955年生まれの僕は学生時代、主に上野鈴本演芸場の高座で、小南の「しじみ売り」や「

また、関西でラジオの人気DJでもあった笑福亭鶴光が1990年から、東京の落語芸術協会に参加、
枝雀譲りの爆笑派、雀々の急逝にショック
落語界に流れる時間は、一般社会よりもゆったりしているので、徐々に、徐々にではあるが、東京で生の上方落語を聴くことのできる場所と機会が増えてきた。
そんな中、11月20日に、上方落語の爆笑派、桂
雀々が亡くなる前後の様子は、たった一人の弟子である桂優々が note(ノート=文章、写真、音楽などの作品を配信するWebサイト)の「週刊! 落語家、桂優々の日々」に書いている。雀々の人となり、師弟の絆などが抑えた筆致で綴られており、胸に迫ってくるものがある。

コロナ禍のために一時、上方落語家が東京に来てくれず、配信で楽しむしかなくなった時期もあった。だが近年は、実力派の桂吉坊らが精力的に東京周辺で独演会を催し、今や全国区の人気者になった桂
僕が今、「もっと東京に来て、暴れてほしい」と強く願っているのが、桂
「蘇った瀬戸内寂聴です」
たいていの観客が「なるほどー」と、つかみのフレーズに納得する。
僕が米輝を「発見した」のはけっこう遅くて、2019年8月の神戸喜楽館で聴いた「千早ふる」だった。
「ちはやぶる神代もきかず竜田川 からくれなゐに水くくるとは。古い時代の歌や。それはまだ大阪が江戸と呼ばれていた頃の話で……」
こんな導入から「歌のわけ」が説明されていく。主人公の竜田川は廃業して故郷の大和郡山に戻って豆腐屋になる。金魚屋の
翌2020年、東京の「桂文珍20日間独演会」で「天災」 (注1) を聴き、神田連雀亭で二度目の「千早ふる」と快作「イルカ売り」 (注2) を聴き、「この人は放っておいたらアカン」となぜか関西弁で思い立って、演芸情報誌「東京かわら版」4月号の連載コラム「今月のお言葉」で米輝を紹介した。
当時、米輝は本気で東京進出を模索しており、東京初の単独ライブを開くという。僕はすぐに予約を入れたが、残念ながら、コロナ禍の広がりのために公演中止となってしまった。
それ以来、米輝を東京で見ることがなくなった。あの風貌だから、会えばすぐわかるはずだが、どこにもいない。
そして今年、米輝はTBS落語研究会に二度呼ばれた。僕と同じことを考えている関係者がいたのだろう。米輝は同会で、4月に「八五郎坊主」を演じ、11月に「牛ほめ」を演じた。「蘇った寂聴」のつかみは相変わらずウケており、まくらで語られる師匠米団治の天然ぶりも楽しかった。
「蘇った寂聴」米輝の異能の高座をたっぷり

11月の研究会の翌日、僕は、アートスペース兜座で催された米輝の「単独落語会」に出かけた。かつて公演できなかった「東京初ライブ」のリベンジと考えていいのだろう。
前座も入れず、一人だけで2時間近く。上方落語ではお馴染みの小道具「見台と膝かくし」を使わず(見台が嫌いなのだという)、前半3席続けて、わずかな休憩を挟んで、後半2席。都合5席の落語を、途中休憩もせず、座布団に座り続け、涼しい顔で演じ通した。
きちんと演じているのに、どこかおかしい古典。普通の日常に、あっと驚く事件が紛れ込む新作。この日の5席は、米輝落語の二つの特徴を見事に取り混ぜ、聴き応え十分だった。
一席目の「予算オーバー」は、挨拶もまくらも「蘇った寂聴」も何もなく、いきなり始まった。はげ頭にお札を何枚も貼り付けた挙動不審な男が、ウーロン茶を「ぐいぐい」ではなく「チュチュチュッ」と忙しなく飲みながら、女性のバーテンダーをしつこく口説いている。本当はウイスキーを注文するはずが、予算オーバーなのでウーロン茶。
「お金は持っているんですよ、頭に。本当はウーロン茶も予算オーバーなんです」
ああもう、この不思議な世界を文章では表現できない。とにかく聴いているうちに「頭にお札男」への嫌悪感が増し、本気で嫌がっているバーテンの気持ちが痛いほど伝わってくる。でも、そういう状況が、じわりじわりと面白くなってくる。
2席目の「変なあくびの稽古」。東京では「あくび指南」の題で演じられる定番の古典を、誰にも教わらず、自分の思いだけで作ったらどんな風になるかと改作してみたのだという。あくびの稽古をしている男は、コワモテの師匠の家で3年間の内弟子を終えたばかり。
「師匠、これまで、アーとかホーとか、あくびそのものしか教わらなかったので、年期明けしたらシチュエーションのあくびを教えてください」「そうかァ、わしはその言葉を待ってたんや。まずは『湯上がりのあくび』からじゃ」
このネタを師匠米団治に聴いてもらったら、「お前な、『あくびの稽古』に失礼やから、題名を変えなさい」と言われた。以来、「変なあくびの稽古」の題で演じているのだという。
米輝落語は珍作ばかりではない。この日の4席目は、「強情」だった。「意地くらべ」という題で五代目柳家小さんなどが演じていた東京の古い新作落語だ。
「ざこば師匠の噺を聴いて、是非やりたいと思った。でもその時、師匠はもう病気だったので、一番弟子の桂
余計な入れ事なしに、全員意地っ張りという登場人物の、こだわりと自負と負け惜しみをきっちりと描き出した。
後の二席、ラーメン屋を舞台にした人情噺風怪談の「ネギ侍」と、腹筋を六つに割るための異様な訓練を描く「シックスパック」も、他に類のない新作だった。
これだけ聴けば、米輝通。と、一瞬思ったけれど、米輝落語はまだまだあるらしい。2020年の「文珍20日間独演会」の楽屋で桂文五郎が「面白いですよ」と教えてくれた「ハムカツの父」を聴いていないし、さらに進化しているはずの「イルカ売り」も、もう一度聴かねばなるまい。
「もっと上方落語を聴きたい」と思うけれど、おそらく東京落語にもまだまだ僕が知らないネタと演者がいるのだろう。キリがないから面白い、我が落語探訪の道は続くのである。
長井好弘 演芸おもしろ帖一覧は こちら !